
神が宿る「隠岐諸島」にある格式高い4つ大社「伊勢命神社・水若酢神社・宇受賀命神社・由良比女神社」の魅力解説!
2025年5月18日神々の島「隠岐諸島」には、4つの有人島に100社を超える神社があるの。
たくさんの神が住んでいる隠岐諸島にある名神大社の4社について前回は紹介したよね。
今回はそれ以外の隠岐諸島にあるおすすめの神社をまとめてみよう。
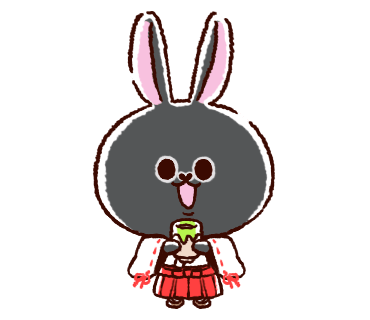

玉若酢命神社 from google
目次
【玉若酢命神社】
玉若酢命神社では、隠岐諸島をつかさどる神の一柱とされている玉若酢命をお祀りしている神社。
天武天皇の勅命により建立されたと伝えられているよ。
また玉若酢命神社は、隠岐国すべての神々を1つにまとめて祀る「総社」としても重要な地位にあるんだ。
この総社という制度はかつて管轄下のすべての神社を参拝する必要があった国司の負担を軽減するために導入された制度なの。
この制度が確立したことによって、国司は1度の参拝ですべての神々に敬意を表することができるようになったんだ。
本殿は1793年建立で、隠岐造りという独自の建築様式で建てられているよ。
隠岐造りは日本各地の主要な神社の要素を組み合わせた建築様式なんだ。

玉若酢命神社 from google
<八百杉>
本殿の前にある杉の木は「八百杉」と呼ばれており、人魚の肉を食べて不老不死を得たとされる伝説の海士「八百比丘尼」に由来するよ。
八百比丘尼は日本中に木を植えたと言われていて、八百杉もそのうちの1つなんだ。
樹齢は1700以上の古木であり、経年により中の幹は空洞化してしまったため、現在は支柱で支えられているよ。
<島後の四大杉とは?>
玉若酢命神社にそびえ立つ「八百杉」は島後の四大杉の1つにもなっているんだ。
残りの2本の杉は隠岐諸島で最も高い山として知られる「大満寺山」の森の中に立っているよ。
1つ目の杉は「乳房杉」と呼ばれていて、御神木となっているの。
樹齢は約800年で、20本以上の大きな下垂根があって、垂れた乳房のような形をしていることから「乳房杉」と呼ばれるようになったんだ。
2つ目の杉は「窓杉」と呼ばれていて、幹に1.8m幅の大きな裂け目があるのが特徴。
窓杉は乳房杉からさらに大満寺山を登っていく必要があるよ。
そして、四大杉の最後の1つは「かぶら杉」
樹齢は約600年で、地上約1.5mのところで6本の幹にわかれているのが特徴なんだ。
このかぶら杉は道路のすぐ脇に生えているので、ドライブがてら見ることもできるからチェックしてみよう。

隠岐神社 from google
【隠岐神社】
海士町にある隠岐神社は1939年に建立された神社。
比較的新しい神社なんだけど、隠岐で最も崇拝されている人物の1人である後鳥羽天皇をお祀りしているんだ。
隠岐神社は後鳥羽天皇の崩御700年を記念して御神徳を広めるために建立されたんだよ。
建築様式は隠岐造りを採用していて、銅板葺きの本殿、祝詞舎、拝殿、神饌所、祭器庫、宝物館、神門回廊、社務所などからなるの。
後鳥羽天皇は1221年の承久の乱で幕府に敗れた後、隠岐諸島に流刑罪になってしまうんだ。
流刑罪といっても、隠岐諸島での暮らしは食料やその他の資源が豊富だったため、それほど過酷なものではなかったそう。
後鳥羽天皇は後世を快適に過ごしたと言われていて、和歌にも造詣が深く、隠岐諸島に来てからも多くの唄を残したんだよ。
後鳥羽天皇の代表的な和歌の数々は、隠岐神社の庭園に建つ石碑に刻まれているんだ。
後鳥羽天皇の生涯の功績については隠岐神社の前にある海士町後鳥羽院資料館で詳しく知ることができるから参拝ついでにぜひ訪れてみよう。
この資料館には隠岐神社の宝物を中心に後鳥羽天皇にちなむ品々が陳列されているよ。

隠岐神社 from google
また隠岐神社は夜間参拝もできるスポットとして知られていて、境内にはたくさんの桜の木があるためお花見の名所としても人気があるんだ。
隠岐神社の桜並木は「隠岐一」とたたえられているよ。
毎年4月14日と10月14日には例祭が執り行われるの。
後鳥羽天皇の御製「我こそは新島守よ隠岐の海の荒き波風心して吹け」に楽と振りを付けた、隠岐神社にだけ伝わる承久楽が奉納されるんだ。

焼火神社 from google
【焼火神社】
島前エリアにある焼火神社は重要文化財に指定されている古社。
島前3島の中で最も高い標高452mの焼火山の中腹に位置しているよ。
1732年改築の社殿は、隠岐最古の木造建築なんだ。
古くから「海上の守護神」として信仰を集めているよ。

焼火神社 from google
隠岐への航海の途中に、遭難しかけた後鳥羽上皇が御神火で導かれたと伝えられていて、海上守護神として信仰されているの。
山から灯る火は、かつて船乗りたちの道しるべとして機能していて、江戸時代に商船で航海していた船乗りたちは、焼火山を通過する際に航海安全を祈願したそう。
また焼火神社の参道は神域として守られてきたたくさんの植物群を見ることができるよ。


奈須神社 from google
【奈須神社】
海士町(あまちょう)の御波と呼ばれる集落にある奈須神社。
旧太井地区の氏神である奈須神社の境内には石神がお祀りされているんだ。

奈須神社 from google
石神は高さ150cm、厚さは60cmほどの立派な石。
何度どけても同じ位置に戻ってくる石を人々が不思議に思ってお祀りしたところ、石が大きく成長して今の大きさになったと伝わっているの。
この神石と同じ性質の石は西へ500mほどいった赤石という地名の場所にあるそう。
石を運搬できるような道はないため、この神石がこの場所にある事実がすごいよね。

壇鏡神社 from google
【壇鏡神社】
島後エリアにある壇鏡神社は那久川上流に建てられた神社。

壇鏡神社 from google
神社の両脇には、高さ約50mの雄滝と、約40mの雌滝の2つの滝があることで有名なんだ。

壇鏡神社 from google
鳥居をくぐって、川沿いの山道を進んでいくと雄滝・雌滝と神社にたどり着けるよ。
神社周辺は水の流れる音や風の音など、自然の音に包まれていて、マイナスイオンをたっぷりと感じられるパワースポットなの。

国賀神社 from google
【国賀神社】
西ノ島にある神社として注目したいのが国賀神社だよ。

国賀神社 from google
国賀海岸のほとりに建てられている国賀神社は、小さな神社なんだけど断崖絶壁に包まれるように造られた祠はまさに絶景。
国賀海岸を訪れた時にはぜひとも参拝しておきたいね。

天佐志比古命神社 from google
【天佐志比古命神社】
知夫里島に唯一ある神社として知られているのが天佐志比古命神社だよ。
地元の人々からは「一宮(いっくう)さん」と呼ばれて親しまれていて、鳥居の扁額にも「一宮神社」と記されているんだ。
この神社の先には、主祭神である天佐志比古命が最初に降り立った場所と言い伝えられるスポットがあるの。
そこは無人島で「神島」と呼ばれていて、今も神聖な場所として知られているよ。

天佐志比古命神社 from google
また天佐志比古命神社には、神社の境内に野外の観覧席があるんだ。
この野外の観覧席は全国でも知夫里島と淡路島にしかないとても珍しいものなの。

天佐志比古命神社 from google
舞台中央が丸く切られて回すことできる「廻り舞台」と呼ばれる歌舞伎舞台が備わった芝居小屋では2年1度、夏季例大祭が執り行われるんだ。
夏季例大祭では島前神楽や、「白波五人男」と呼ばれる歌舞伎が村人たちによって演じられるよ。

三穂神社 from google
【三穂神社】
中ノ島の南部にある崎集落にある三穂神社は、後鳥羽上皇ゆかりの場所にあるんだ。
境内には後鳥羽上皇御駐泊址の石碑もあるよ。
後鳥羽上皇は1221年(承久3年)に承久の乱で朝廷に敗れた後、隠岐へ流罪になってしまうんだけど、三穂神社は後鳥羽上皇が隠岐で最初の夜を過ごした場所なんだ。

三穂神社 from google
三穂神社の麓にはくにびき神話佐伎の里公園が整備されているよ。
出雲の国には伝説が残っていて、出雲が未完成だったころに八束水臣津野命が4つの国から土地を引き寄せ縫い合わせて島根半島ができたそう。
この4つの国の1つが、三穂神社がある崎集落なんだって。

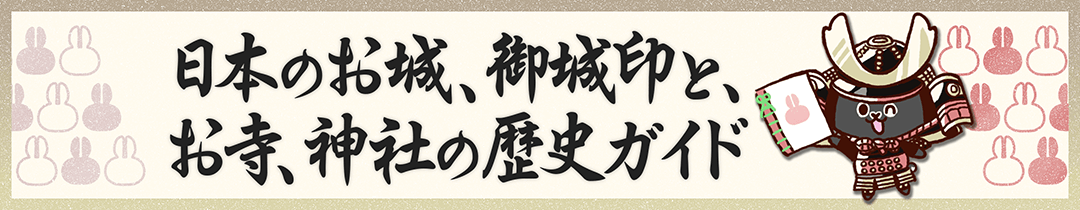








-5.jpg)



