
女性の一生を守る「粟嶋堂崇徳寺」は人形供養のお寺として有名!
2025年4月21日
神々の島・隠岐諸島に行ったら絶対行きたいおすすめの神社を徹底解説!
2025年5月18日
島根・鳥取の県境から北方約60㎞に位置する島根・隠岐諸島は、日本最古の歴史書と言われる古事記にも登場する、歴史ある島だよ。
隠岐諸島は小さい島でありながら、4つの有人島には100社を超える神社があるんだ。
今回はその中でもとくに有名な隠岐諸島にある4つの大社「伊勢命神社・水若酢神社・宇受賀命神社・由良比女神社」を紹介するよ。
【100社以上の神社あり?神々が宿る「隠岐諸島」とは?】
隠岐諸島は現存する日本最古の歴史書である古事記の「国生み神話」で神様が生んだ8つの島になっている歴史ある島なんだ。
8つの島とは淡路島・四国・隠岐・九州・壱岐・対馬・佐渡・本州のことだよ。
イザナギとイザナミが淡路島・四国についで3番目に生んだ島が「隠伎之三子島(オキノミツゴノシマ)」、現在の隠岐諸島なの。
ちなみに隠伎之三子島(オキノミツゴノシマ)とは、隠岐諸島の中で最大の島後を「親島」、知夫里島・西ノ島・中ノ島を「子島」として、親島に率いられた3つの子島という意味と言われているよ。
隠岐諸島は約180の島と4つの有人島があるの。
海洋生物や漁業などの人の営みなど、隠岐諸島を取り巻く環境そのものが「ユネスコ世界ジオパーク」に認定されているんだ。
隠岐諸島は小さい島でありながら、4つの有人島にはなんと100社を超える神社があるよ。
たくさんの神が住んでいる島として知られていて、日本最古の全国神社リスト「延喜式神名帳(927年)」に記された神社はなんと16座もあるんだ。
そのうち、強い力を持っている神をまつる神社には「名神大」の格が与えられていて、隠岐諸島には名神大の格を持つ大社が4つもあるの。
島根県エリアで名神大社は6社しかないので、隠岐諸島にいかにたくさんあるかが分かるよね。
<流刑の地としても有名>
隠岐諸島は遠流の地として、聖武天皇が即位した724年に定められているの。
江戸中期になって一般の罪人が3000人ほど流されるようになるまでは、天皇や公家、役人などの政治犯が配流となっていたんだ。
隠岐に流された著名な人物には、後鳥羽上皇や後醍醐天皇、小野篁などがいるよ。
隠岐が遠流の地となったのは、都から遠く離れているという理由だけではないの。
島での生活に問題が少ないためと言われていて、流された貴人が飢えてしまったり、生活に危険を覚えたりするような場所ではなかったそう。
隠岐は離島ではあるものの、作物は豊かであったんだ。

【隠岐諸島にある名神大社4社を徹底解説】
名神大社とは、霊験あらたかな名神祭の対象となる神様たちをお祀りしている神社のこと。
古代における由緒ある社格の1つとされているんだ。
隠岐諸島には名神大社に選定されている神社が4社あるよ。
延喜式神名帳には日本全国の由緒ある神社が2861社記載されているんだけど、その中で名神大社に指定されたのはわずか224社だけなの。
そのほとんどは、当時の都であった京都やその近郊に位置していたそう。
遠隔地である隠岐諸島に4社もの名神大社があったという事実は、その当時から朝廷との強い繋がりを示す証拠となっているんだ。
ここでは隠岐諸島にある名神大社4社についてまとめてみよう。

水若酢神社 from google
<水若酢神社>
隠岐国の一宮である水若酢神社は、水若酢命をお祀りしているよ。
一宮の称号を持っているので、旧隠岐国で最も格式の高い2つの神社の1つなんだ。
御祭神である水若酢命は、海から現れて現在の神社がある場所にやって来たと言い伝えられていて、隠岐の国土開発と日本海鎮護をされた神様なの。
創建の由緒は不明だけど、社伝によると人徳天皇の時代(4~5世紀ごろ)に創建されたと伝われているんだ。

水若酢神社 from google
水若酢神社の本殿は「隠岐造り」と呼ばれる建築様式で、国の重要文化財にも指定。
西暦偶数年の5月3日には水若酢神社祭礼風流が開催されているよ。
この例大祭は島後の三大祭りとして知られていて、日本古来の山車が曳かれ、流鏑馬の神事も行われるんだ。

水若酢神社 from google
水若酢神社の参道脇には映画「渾身」の舞台にもなった土俵が設けられているよ。
20年に1度本殿屋根の葺き替え時には、隠岐古典相撲が夜中行われるんだ。
この相撲は2番勝負で行われるもので、1本目に勝った方は2本目に勝ちを譲って1勝1敗にすることが特徴なの。
隠岐古典相撲は両力士が勝敗のしこりを残さずにお互いをたたえ合うことから、島の人々の人情を評して「人情相撲」とも呼ばれているよ。
相撲は今日ではスポーツとしてのイメージが強いけれど、実は神道と密接な関係があり、神々への奉納として神社で行われる儀式として始まったんだ。

水若酢神社 from google
また水若酢神社の近くには西洋建築があって、隠岐郷土館として島の民俗を展示しているよ。
この西洋建築の建物は1885年創建で、かつては行政庁舎や郵便局として使用されていたもの。
水若酢神社参拝ついでに、隠岐郷土館にも行ってみよう。

由良比女神社 from google
<由良比女神社>
西ノ島町にある由良比女神社も水若酢神社と同じく、平安時代末期には隠岐国一宮に定められていた、由緒ある格式の高い神社。
名神大社の1つで創建は古く、仁明天皇の時代(842年)官社に預かったと記されているよ。

由良比女神社 from google
由良比女神社は「イカ寄せ」として知られているの。
伝説によると、この社の元は知夫里島の鳥賊浜にあったそう。
西ノ島の由良へ移されてからは、鳥賊浜にイカの群れが来なくなり、その代わりに由良へイカが集まったと言われているんだ。

由良比女神社 from google
さらに御祭神である由良比女命が芋桶に乗って出雲大社から隠岐へ帰る時にイカたちがいたずらで女神の手に嚙みついてしまい、女神を怒らせてしまったそう。
そのお詫びのしるしに由良の浜にはイカの群れが押し寄せるようになったと伝わっているんだ。
かつては秋~冬にかけて回遊するイカが入り江に群れをなし、地域の人々は素手でイカを捕まえていたの。
近年ではイカの数は減少しているそう。

由良比女神社 from google
イカ寄せの御利益があるとされる由良比女神社の境内には、燈籠や拝殿にイカの彫刻が刻まれているんだ。
また由良比女神社がある西ノ島町の建物の壁やマンホールにもイカが描かれていて、ゆるキャラにもイカが登場するよ。
神社の目の前には浅い入り江の「イカ寄せの浜」があるからぜひチェックしてみよう。

宇受賀命神社 from google
<宇受賀命神社>
宇受賀命神社は海士町にある名神大社。
鳥居から神殿までの間に広がる田んぼがとても綺麗で、稲穂が青々と茂る夏や、秋の黄金色に染まる時期は絶景なんだ。
この神社ではあ、島の守護神である宇受賀命をお祀りしているよ。

宇受賀命神社 from google
創建は842年よりも古く、古来より朝廷の崇敬が篤かったため、時の有力者より社領や神田などたくさんの寄進があったの。
伝説によると西ノ島町の比奈麻治比賣命の美しさに惹かれた宇受賀命は、同じように姫に求婚する大山神社の神様と力比べをして勝利して、見事姫と結ばれたんだって。

宇受賀命神社 from google

宇受賀命神社 from google
宇受賀命と比奈麻治比賣命の間には柳井姫が生まれ、「奈伎良比賣神社」の御祭神になったよ。
比奈麻治比賣命が柳井姫を産んだ場所は明屋海岸という絶景スポットなの。
明屋海岸から宇受賀命神社にいたる海岸線の道は、日本海唯一の神々の婚姻に由来して縁結び・子宝・夫婦円満のご利益がある道として知られているんだ。

伊勢命神社 from google
<伊勢命神社>
伊勢命神社は西日本最大級の黒曜石の産地である久見地区にある名神大社。
黒曜石は鋭利な切れ味から、先史時代の石器づくりの材料として重宝されていたの。
日本有数の良質な黒曜石が採れた隠岐では、黒曜石の産出地域として約3万年も前から日本全国で取引を行っていたんだ。

伊勢命神社 from google
伊勢命神社の神は外部の勢力からこの地域を守ると信仰されていて、とても重要な神様として祀られていたの。
また、続日本後記(869年)には「仁明天皇嘉祥元年(848年)、明神の列に預かりし趣名記せられ延喜の制に於いては名神大に列せられた」と記載があって、六国史に名神大社列格の理由を明示する数少ない例となっているんだ。

伊勢命神社 from google
毎年7月には例祭が開催されており、弓矢を持って鎧兜を身に着けた武者が先導するよ。
この形は隠岐でも珍しいんだ。
例祭に合わせて伊勢命神社の境内にある神楽殿では「久見神楽」が夜通し行われるの。
この久見神楽は畳2枚ほどの広さで舞う古い形を残しているよ。

伊勢命神社 from google
伊勢命神社の本殿は、水若酢神社と同じ「隠岐造」と呼ばれる建築様式。
屋根は出雲大社の「大社造」、庇の部分が春日大社の「春日造」、全体的な柱の立て方は伊勢神宮の「神明造」になっているよ。
3つの建築様式をあわせていて、隠岐ならではの様式なんだ。

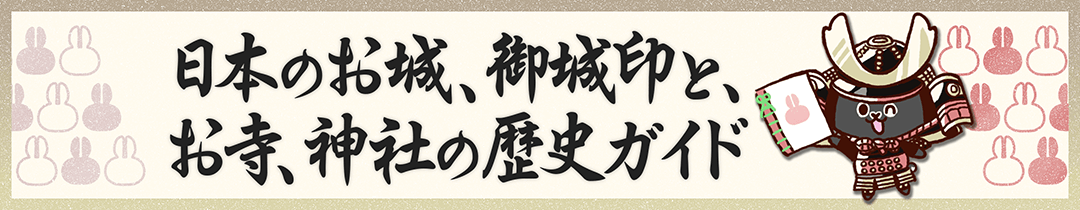







-5.jpg)



